遺言
遺言書は、あなたの大切な財産や思いを大切な人々に伝えるための重要な手段です。遺言書があればご家族やご親族の間で不必要な争いを避け、スムーズに遺産分割を行うことができます。
経験豊富な司法書士が対応します。
当事務所の遺言サポート内容
・遺言書の文案作成
・必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わせを代行
・公証人との内容・日程の調整
・公正証書遺言の証人としての立会
自筆証書遺言書保管制度とは……自筆証書遺言を法務局で保管することで、紛失や改ざんの恐れをなくし、検認手続きを不要にする制度
遺言に関してお困りごとがある方は、お気軽にご相談下さい。
遺言の必要性が高い場合
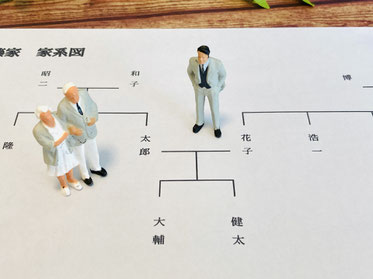
- 相続人となる方が一人もいない場合
- 内縁の配偶者がいる場合
- すでに亡くなっている子供のお嫁さんのお世話になっている場合
- 夫婦間に子供がいない場合
- 相続人の中に行方不明の方がいる場合
- 家業を継ぐ特定の子供に事業用財産を継がせたい場合
- 先妻との間に子供がいるが、現在後妻がいる場合
- 離婚状態にある別居中の配偶者がいる場合
- 相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる場合
- 相続人同士の仲が良くない場合
- 残す財産分配や割合を自分で決めたい場合
- 相続人が大勢いる場合
遺言には、法律で定められた次のものがあります。
遺言の種類
「遺言者が一人で作成できる」
「遺言書の内容を公証人が証明する」
「遺言書の存在のみ公証人が証明する」
※ 2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができましたので、秘密証書遺言特有のメリットがあまりなくなりました。さらに、費用(公証人役場手数料の11,000円)や検認手続きも必要となることからおすすめいたしません。
自筆証書遺言書
| 作成 |
遺言者本人が遺言書の全文、日付、及び氏名を自書する。(財産目録に限りワープロなどの使用が可能) |
| ポイント |
・紛失や偽造のリスクがある。 ・遺言書が無効にならないよう細心の注意が必要。 |
| 保管 |
・自宅で保管する。 ・専門家に預ける。 ・法務局の制度を利用する。 |
| 検認 |
法務局以外で保管した場合は、 |
| 費用 |
務局で保管する場合は手数料が必要 (1件3,900円)。 |
公正証書遺言書
| 作成 |
公証役場で公証人と証人2人が立会って行う。 |
| ポイント |
・公証人という法律の専門家が関与するので形式の不備で遺言が無効になるおそれがない。 ・遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合、公証人が出張して作成できる。 |
| 保管 |
原本は公証役場で保管、 |
| 検認 |
検認の必要がない。 |
| 費用 |
公証人、証人、司法書士への手数料が必要。 |
遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。
公正証書遺言の作成や保管制度の利用により、遺言書の紛失や改ざんリスクは無くせます。
しかし、遺言書の内容による無効リスクの有無やそもそも自分が希望する内容の遺言書となっているかの確認は公証役場や法務局では確認してくれません。
そのため、遺言書を作成して相続トラブルを回避したい、自分が希望した人物に財産を遺したいのであれば、遺言書の作成を司法書士に依頼するのがおすすめです。
遺言の必要性
遺言を作成するメリット

自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産の分配や割合を自ら意思で決定
することが可能となり、相続人に確実に自分の意思を伝えることができる。

遺言を残すことで相続争いを防ぐことができる。
多くない財産についても、兄弟姉妹間で遺産の分け方で争う事例が後を絶ちません。

遺言書があると、相続人が遺産分割協議を行わずに済み、相続人の手間や精神的な負担を大幅に軽減できます。

相続人以外への遺産の分配が可能なる。遺言書があれば、法定相続人ではない内縁の配偶者や特定の友人、団体に遺産を渡すことが可能です。
遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の権利者を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
よくある質問
Q. 遺言がないときは、どうなりますか?
① 法定相続
遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
② 遺産分割協議が必要
民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので(民法900 条)、遺産の分配や割合を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
しかし、少しでも多く、少しでも良いものを取りたいというのが人情なので、協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判によって解決してもらうことになりますが、この場合でも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、遺言に基づいて相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあると考えられます。
③ 相続人間の実質的な公平が図れない場合がある
法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、これをそれぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。
例えば、法定相続では、子は、皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子(家産の維持・増加に努めた子)と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑であるうえ、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。
そのため、遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
当事務所では
初回の相談を無料で受け付けております。
お客様のご状況に応じた最適な
アドバイスをさせていただきます。
相続に関する不安や疑問が
ございましたら
ぜひ、ご相談ください。
ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。
